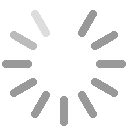000
アウディ(総合)
+本文表示
レクサスなんかより数段高いわバーカ(笑)
627
628
>>621
?太いアクセ?なんで知ってる?
ホスラブで見せた事なんてないのによ
629
630
631
『豚雑煮の部屋』
築45年のワンルーム。
天井は低く、壁紙には染みが浮いている。部屋の隅にはペットボトルの山。1.5リットルのコーラの空ボトルが、ビニール袋にも入りきらず床を埋めていた。
住人は坊主頭の中年男。分厚い眼鏡の奥で、濁った目が光る。
身にまとっているのは、柄物のブランド物――派手なロゴのジャージやベルト。だが新品の輝きはなく、脂の匂いと古い煙草の灰にまみれていた。
愛車は中古のアウディTT。
夜な夜なスーパーにコーラを買いに走るときだけ、狭い路地にその存在を誇示するように停まっていた。
彼の一日は単調だ。
朝起きて病院に行き、薬をもらい、帰ってきてコーラをラッパ飲みする。
昼過ぎにはネット掲示板を開き、匿名の海に自らの顔や身体を晒しては、反応を求める。罵倒も笑いも、彼にとっては「繋がり」だった。
632
ある日、掲示板で「豚の雑煮」と呼ばれた。
彼が正月に一人で作った豚肉たっぷりの雑煮を写真に載せたときのことだ。脂が浮いた鍋、白濁した汁。それを見た誰かが嘲笑した。
――「豚が豚食ってるだけじゃん」
彼はその言葉を何度も読み返し、胸の奥に沈めた。
夜、部屋で煙草をふかしながら、またコーラを開ける。
黒い液体が喉を通るたびに、笑い声が蘇る。
でも、やめられない。アルコールを断ってから、コーラだけが唯一の酔いだった。
――「まだ、俺は終わってない」
そう呟いて、掲示板に新たな写真をアップする。
顔も局部も隠さない。哀れみも、嘲りも、全てを受け止める覚悟のように。
画面の向こうで、誰かが笑っている。
誰かが罵っている。
でも確かに、自分はまだ「誰か」と繋がっている――。
古いワンルームの蛍光灯の下、彼は今日もコーラを開ける。
甘ったるい炭酸が、静まり返った夜にシュッと弾けた。
633
「続、豚の雑煮」――
その言葉は、彼の胸の中でいつまでも腐敗したように残っていた。
翌朝、鏡を見た。
丸い顔、脂の浮いた肌、分厚い眼鏡の奥で虚ろな細い目。
――「本当に豚に見えるのか?」
自分に問いかけても、返事はなかった。
病院に向かう道すがら、彼は中古のアウディTTの窓に映る自分を見た。
車だけはまだ、彼のプライドの残り火だった。
「これがある限り、俺はまだ“負け”じゃない」
そう思うことで、辛うじて立っていられた。
だが、帰宅して掲示板を覗くとまた同じ言葉が並んでいる。
「雑煮豚」
「脂まみれの中年」
「コーラ中毒」
怒りが込み上げた。
彼は部屋の机に座り、震える手で新しいスレッドを立ち上げる。
タイトルは――
《俺を豚扱いする奴らに告ぐ》
そこに長文を書き連ねた。
自分がどんなに孤独か、どんなに努力しているか、そしてどんなに車を大事にしているか。
“笑うなら笑え、俺はまだ生きてる”
最後にそう書き込み、写真を添えた。
634
写真には、愛車TTのボンネットに鍋を置き、豚雑煮をよそって食べる自分の姿。
メガネが光り、坊主頭が蛍光灯に照らされ、膨れた体がどっしりと写っている。
数分後、レスが付いた。
――「笑ったw」
――「すげー開き直りだな」
――「逆に好感持った」
彼はその言葉に目を細めた。
馬鹿にされているのか、褒められているのか分からない。
けれど、久しぶりに心臓が強く打っているのを感じた。
夜、彼はまたコーラを開ける。
炭酸が弾ける音が、拍手のように聞こえた。
――「まだ、続きがある」
彼はそう呟き、掲示板を見つめた。
次はもっと派手なことをしてやろう、と心のどこかで決意しながら。
635
掲示板に上げた「豚雑煮とアウディTT」の写真は、予想以上に話題になった。
嘲笑、罵倒、そして少しの称賛――。
それら全てを一気に浴びた彼は、胸の奥に熱を覚えていた。
「俺はまだ、ネットの向こうで“見られてる”」
その実感が、何よりの薬だった。
病院でもらった錠剤より、コーラより、煙草より効いた。
次はもっとインパクトのあることをしなければ。
そう考えた彼は、押入れから派手な柄物ブランドのスーツを引っ張り出す。
かつて無理して買った、ポールスミスのスーツ。
今となっては腹が突き出て、ボタンが閉まらない。
だが、それがいい。笑わせてやればいい。
夜更け、アウディTTをコンビニの駐車場に停め、車の前に三脚を立てる。
自撮りだ。
缶のコーラを三本、一気にラッパ飲みし、その空き缶を足元にばら撒く。
636
腹を突き出し、両手を広げ、ジャケットをはだけた。
顔も局部も、もちろん隠さない。
シャッターを切った瞬間、冷たい夜風が坊主頭を撫でた。
――「これが俺だ」
数分後、掲示板にその写真が投稿された。
レスが止まらない。
「腹出すぎww」
「また雑煮豚きた!」
「TTの前でやるセンスだけは認める」
「ここまでやると逆に尊敬」
彼は画面を見つめながら、心臓が高鳴るのを感じた。
嘲笑も罵倒も、もう怖くなかった。
むしろ必要だった。
――「次はもっとやる」
彼は決意する。
掲示板で名を残すために。
孤独な四畳半から世界へ繋がるために。
部屋の隅には、まだ新品の花火や使われていないガスバーナーが眠っている。
彼の頭には、次の“舞台”のイメージがもう浮かんでいた。
夜の闇に、コーラの炭酸がまたシュッと弾ける。
それは拍手のように響いていた。
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。